
仕事の生産性を高める最強無料アプリ7選(2023年最新)
Marketing Blog マーケティングブログ
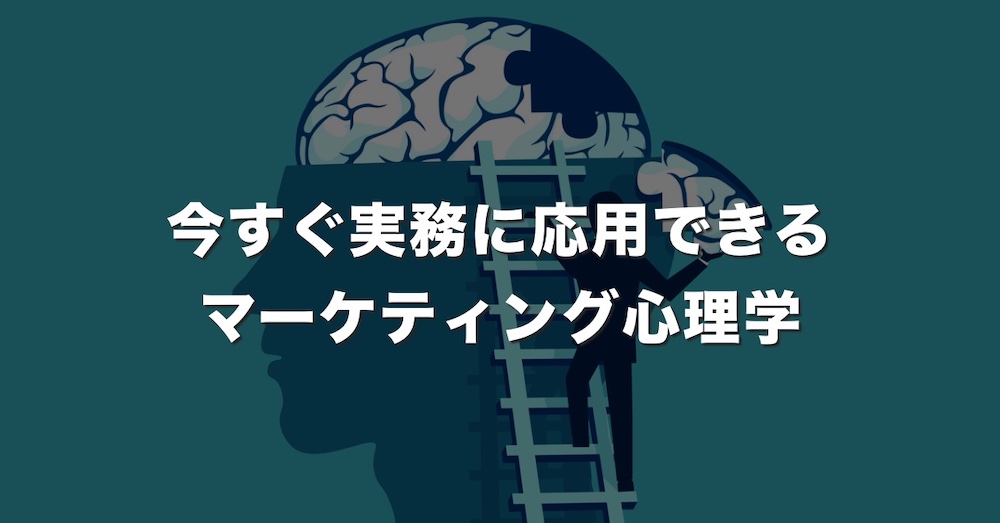
自身が策定したプロモーション戦略や、プロモーション企画について上司に説明をする際、「なぜそう考えたのか?なぜその選択をしたのか?」という質問に明確に答えられなかった経験はありませんか?
現代マーケティングは実にさまざまな手段があり、世間で一般的に行われているマーケティング施策を参考に企画を進めていると、細かいところまで根拠を言語化するのが難しいことも多いと思います。
ただ実は「プロモーション戦略」や「コンテンツ設計」「デザイン」の根底には、人間の行動心理学を応用したマーケティング心理学がよく使われており、これを理解すれば根拠を言語化しやすくなります。
今回はその「マーケティング心理学」をテーマに、よく世間で見かけるキャッチコピーや販売促進施策の元となっている主要な「マーケティング心理学」を6つ紹介していきます。
この記事で学んだマーケティング心理学は、さまざまな施策のプランニングにすぐに応用できますし、自分が企画した販促施策のプレゼンの際にもはっきりと「なぜそうするのか?」を答えられるようになります。ぜひ最後までお読みください。
マーケティング心理学とは、商品・サービスからのアプローチに対する消費者の反応と、それらが購買行動に与える影響を研究して、マーケティング戦略に応用する行動心理学の一種です。
広告、ブランディング、製品開発、販売戦略などのマーケティング企画を行う際に、あらかじめ消費者の心理反応を深層心理レベルで理解することで、明確な根拠に基づき効果的な戦略を策定することができます。
心理学がマーケティングに果たす役割は、人々がなぜ商品やサービスを購入するのかを理解することで、それらをうまく売るための戦略を作ることです。ここではマーケティング心理学を学ぶべき2つの理由を紹介します。
マーケティング心理学を学ぶことによって、人々が何かを購入判断するときに何を考え、どう行動するかの法則を明らかにします。これを知ることで、マーケターは人々が商品を買う可能性を高めるためのコピーやメッセージを作ることができるようになります。
マーケティング心理学は、人々の感情や考え方が購買行動にどのように影響するかを教えてくれます。
例えば、好きなブランドに対する良い感情は、そのブランドに忠実になる可能性を高めます。
また、消費者の目の前にある物事が、どう捉えられるかによって商品の選択に影響を与えます。
これらの要素は、商品を売るための戦略を作り、消費者とより良い関係を築くための重要な知識となります。
ここからはすぐ実務に応用できる6つのマーケティング心理学を紹介していきます。
「アンカリング効果」は、人々が最初に提示された情報(アンカー)に強く影響を受け、その後の意思決定や評価に最初の情報を基準として使用するという心理学の原理です。
マーケティングにおける一つの具体的な活用例は、商品の価格設定です。
例えば、ある商品が通常1万円で販売されているとします。この1万円は消費者の心に「アンカー」として定着します。
その後、その商品がセールで8,000円になったとき、消費者はこの新しい価格を元の「アンカー」である1万円と比較します。その結果、消費者は8,000円が大変お得に感じ、購入を決断する可能性が高まります。
よく化粧品や健康食品などのオンライン通販で「通常価格5,980円のところ初回お試し価格980円」のような訴求を目にしますが、これもアンカリング効果を狙ったものと言えます。
このように、アンカリング効果は消費者の価格認識を操作し、購入意欲を引き出す強力なマーケティングツールとなります。
一方、アンカリング効果を狙って値引きを行う際は「景品表示法」に抵触しないように注意も必要です。最初に表示されている通常価格(元値)が適正でない、あるいは実態のない場合は景品表示法の違反となる上、販売者のブランド毀損にも繋がってしまいます。
「ザイオンス効果」とは、人が何かに接触する頻度が増えると、それに対して好感を持つようになる心理効果のことを指します。
あなたも普段の生活の中で「今まで聞いたことのないメーカーの商品はなかなか手に取らないけど、何度もCMや店頭などで目にしたことのある商品を無意識にカゴに入れていた」
といった経験があるかと思います。実はこの現象もザイオンス効果によるものです。
ザイオンス効果をマーケティングの観点で見てみましょう。
商品の広告を何度も目にすることで、消費者は商品に対して好感を持ち、購入につながることがあります。
また、企業のロゴやブランドを頻繁に目にすることで、企業に対して好感を持ち、商品やサービスを購入する可能性が高くなることもあります。
例えば、大手企業がWEB上やSNSで目にするデジタル広告だけではなく、テレビや交通広告などのマス広告にも注力し、幅広い媒体で訴求を行うのは消費者とブランドとの接触頻度を増やすことで無意識的に好感を持たせる「ザイオンス効果」を狙った戦略と言えるでしょう。
もう少し掘り下げれば、SNSで毎日投稿をすることや、メールマガジンを毎週配信するのも消費者とブランドとの接触機会を増やすことを目的とています。
ザイオンス効果を活用する際は、いくつかの注意点があります。
接触する頻度が高すぎると、人々は単なるノイズと見なすようになってしまうためです。そのため、接触する頻度には注意が必要です。
ただ頻繁に広告を出しても、消費者が目にするコンテンツが人々の興味を引くものでなければ、効果は期待できません。そのため広告のコンテンツには、人々の興味を引き心を動かす要素を盛り込むようにしましょう。
ザイオンス効果はあくまでも心理効果の一つであることを忘れてはいけません。ザイオンス効果だけで商品やサービスを売り込むことは困難です。ザイオンス効果を活用する際には、その商品を購入したいと思わせるマーケティング手法と組み合わせて、効果を高めていくようにしましょう。
「バーナム効果」とは、曖昧で一般的なことを言われているのにも関わらず、あたかも「自分のことを言い当てられている」と感じてしまう心理効果のことを指します。
40歳くらいの人が占い師から「最近心身の不調を感じることが増えたでしょ?」と言われたとき、40歳にもなれば大抵の人がどこかしら不調があるはずなのに、直接それを言われた本人は「えっ、心を読まれている?」と感じてしまうでしょう。これもバーナム効果の1つです。
ランディングページや記事広告の冒頭で「◯◯◯なお悩みありませんか?(ありますよね)」といったメッセージを見かけたことはありませんか?
これは最初にターゲットに当てはまる「課題や悩み」を明確に示すことで「自分ごと化」させることが狙いです。改めて課題提起することで商品やサービスに興味を持ってもらうための動機づけを行っているのです。
また、バーナム効果は営業時のセールストークでも活用できます。
リード客との商談の際に、多くの企業が抱えている課題に当てはまる質問を投げかけ、それを解決する手段として自社商品を紹介する手法です。
課題を見事に言い当てられたリード客にとって、その営業担当者は良き理解者と感じるようになり、それがきっかけで商談が前進する可能性も高くなるでしょう。
一方、バーナム効果を活用する際にも注意点があります。
バーナム効果は、その問いかけがあなた個人に向いているように認識させることが重要です。多くの人に当てはまる内容だとしても「あなた一人」に対して伝えることで「自分ごと化」してもらいやすくなるからです。
具体的には「〇〇でお悩みのみなさん」ではなく「〇〇でお悩みのあなた」と言ったように、個人を指す表現を使った方がバーナム効果が一層有効になります。
伝える内容の信憑性が高くないと、人は騙されていると感じてしまい、その効果はマイナスに働く可能性があります。しっかりとターゲットの課題や悩みを研究して、事実に沿った内容を伝えるようにしましょう。
バーナム効果を利用して消費者の興味を引く場合でも、倫理的な配慮が必要です。過度な誇張や相手の不安を煽るような表現によって消費者を惑わすことは避け、消費者の利益や便益を最優先に考えるべきです。
「返報性の原理」とは、相手に何かしてもらうと、無意識的にそれに見合った返報をするように促される心理効果です。
人々は他者との関係を構築する際、お互いに物事や気持ちを「GIVE&TAKE」し合うことで、協力や信頼関係を促進することができます。
マーケティング心理学における「返報性の原理」は、企業側から先に消費者にGIVEを提供することで、商品を購入(TAKE)してもらうことが狙いとなります。
「返報性の原理」がどのようにマーケティングに活用されるかいくつか例を挙げてみましょう。
オフライン領域では「スーパーマーケットでの試食」や「飲食店の1品無料サービス」、「ホテルのウェルカムドリンクの提供」、「イベント会場や街角での無料サンプルの配布」などが、GIVEに該当し、そのお返しとして商品を買ってもらう「返報性の原理」を狙った施策と言えるでしょう。
また、デジタル領域であれば、WEBサイト上やSNSなどで「業務改善に役立つノウハウを無料でプレゼント」したり、ECサイトで「購入金額の数%をポイント還元」したりするのもこの原理を利用して購買意欲を刺激していると言えます。
返報性の原理を活用する際の注意点は以下の通りです。
GIVEの内容が不十分だと人は不快に感じてしまい、効果が期待できません。
そのため、GIVEの内容は購入してほしい商品やサービスの価値に見合うようにしましょう。
一時的な利益追求や偽りの恩恵を提供することは、逆効果となり信頼関係を損なう可能性があります。真に価値や利益があるものを提供し、消費者との相互的、かつ対等な関係を構築することが、返報性の原理を成功させるポイントです。
GIVEからTAKEのタイミングが遅すぎると人はそのことを忘れてしまい、効果が期待できません。 GIVEとTAKEはできるだけ時間をあけずに連動性を持って計画することが大切です。
「損失回避の心理」は、行動経済学や心理学の概念で、人々が損失を避けることに対して非常に敏感であるという現象を指します。人々は同じ価値の損失と利益を受ける場合でも、損失を避ける方を優先して行動する傾向があるということです。
過去の実証実験により損失回避の法則には3つのパターンがあることが分かっています。
ここでは各パターン別にマーケティングへの活用例を挙げていきます。
この心理パターンを活用した最もわかりやすい言葉は「今買わなきゃ損!」でしょう。
ネット通販やダイレクトマーケティングの世界でもあらゆる所で「数量限定」「先着●名様だけ」「期間限定」といった枕詞が使われています。
ECサイトを使っていると「あなたのポイントは●月●日で失効します」という通知が届きますが、これも今ポイントを使わないと損をしてしまうという心理を突いています。
ダイエットや育毛剤などのコンプレックス解消を目的とした商材はあまり聞いたことのないブランドの物がたくさん出回ってますよね。聞いたことのない少々怪しく感じる商品でも、コンプレックスを解消できる可能性があるなら思い切って買おうという心理が働いています。
競馬やパチンコなどのギャンブルも同じで、最初に3万円負けたにも関わらずその3万円をとりもどすためにさらに追加でお金を投下してしまう人はたくさんいます。
消費者のコンプレックスやネガティブな部分にフォーカスしそれを解消するための商品・サービスはこの心理を突いたビジネスと言えます。
この心理は、サイコロを振って「偶数がでたら3万円もらえる」「奇数が出たら2万円払う」というゲームがあった場合、理論上の期待値はプラスにも関わらず参加しない人の方が多くなるというものです。
プラスになる可能性のほうが高くても、損をしたくない気持ちの方が勝るのが「損失回避の心理」です。
この心理がマーケティングに活かされているのが、通販の「効果を感じなかったら全額返金保証」や、WEBサービスの「最初の30日間は無料」のような施策です。
気に入らなかったら「なかったことにできる」のが、消費者に安心感を与え購入ハードルを下げているのです。
そのほかにもキャッチコピーを考える際に「この商品を使えばメリットがあります!」よりも「この商品を使わないとデメリットがあるかも……。」と謳い、消費者の損をしなくない心理に働きかけるようなライティングテクニックもあります。
損失回避の原理は、消費者の購買行動を促す上で大変有効ではありますが、消費者を動かそうと必要以上に不安を煽るような表現を使ったり、アプローチがしつこいと消費者が疲弊し逆効果になってしまうので注意しましょう。
損失回避を訴求する際には、顧客が損失を回避するために行動を起こすことが簡単で、実行しやすいようにする必要があります。商品やサービスの利用が消費者の損失回避
「ハロー効果」とは、ある人や物事の評価をするとき、1つの目立った印象が全体的な印象にも影響を及ぼすという心理効果です。
例えば、容姿が魅力的な人は、その魅力から他の側面(知性や親切さなど)も良いものだと仮定されがちです。同様に、有名なブランドが提供する商品は、そのブランドの評判から高品質であるとみなされることがあります。
ハロー効果は、マーケティングにおいて広く活用されています。
例えば、有名人を広告に起用することで、「この人が使っている商品ならきっと良いものに違いない」と、商品への好感度を高めることが期待できます。
また、商品やWebサイトのパッケージやデザインをクオリティの高いものにすることによって、商品に対する印象がよくなり、価値を高めることに繋がります。
我々アライブがマーケティングやブランディングに「デザイン」を重視しているのも、この「ハロー効果」が背景にあります。
ハロー効果を活用する際は、いくつかの注意点があります。
最初に持ったイメージが悪印象だと、それに連動して他の要素まできっと悪いものだろうと思われてしまう危険性があります。消費者が認知する段階でイメージを下げてしまうと、どんなに高品質で利便性が高くてもそれを知ってもらうために時間とコストを浪費してしまう可能性があるので注意しましょう。
第1印象がすぐに忘れられてしまうようなレベルだと、ハロー効果も薄いものになってしまいます。競合他社の製品と比べて、独自性のある特徴をアピールしていくことが大切です。
誇大表現や偏った情報を用いて印象づけをしてしまうと、個人の客観的な判断や公平さを阻害する可能性があるので注意が必要です。商品のキャッチコピーや訴求内容に誇張や虚偽が発覚してしまえば間違いなくブランド毀損につながります。
偏った一部の特徴や評価だけを使うのではなく、総合的な情報や客観的なデータを考慮することが重要です。
今回の記事では「今すぐ実務に応用できるマーケティング心理学」について解説していきましたがいかがだったでしょうか?
この他にも、マーケティングにはさまざまな行動心理学が応用されています。
我々アライブが提案するデザインや、UI/UXの設計、プロモーション戦略にもこれらのマーケティング心理学が根拠となっているものが多々あります。
マーケティングは細部にまでこだわることで、最終的な成果に大きく影響します。
本気で集客改善に取り組みたいという企業様はぜひアライブに一度ご相談いただけると嬉しく思います。
アライブはデザインとマーケティングの掛け算により、多くの企業様のブランド力向上や集客改善をサポートしてまいりました。
これまでに蓄積したマーケティングのノウハウを元に、お客様の本質的な課題を見つけ出し適切な改善案をご提案させていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
