
話題のChat GPTを日々の業務に活用する方法
Marketing Blog マーケティングブログ
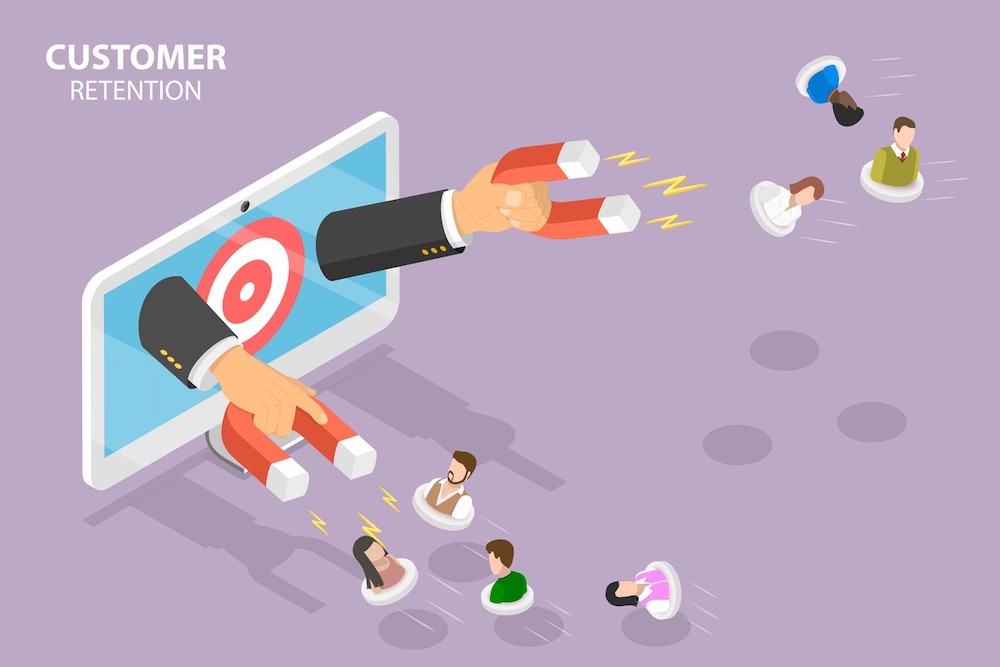
「これまで社内で新規顧客の獲得に注力してきたけど、時が経つにつれて新規顧客の獲得効率が悪くなってきた。」
そんな経験をされた事があるマーケターの方もいらっしゃるかと思います。
新規顧客の獲得はマーケティングには欠かせないものですが、人口減少や消費者の趣味趣向の多様化、類似商品の供給過多などにより、その難易度が高まってきているのも事実。
そんな背景もあり、ここ数年の間に既存顧客との良好な関係を築く「リテンションマーケティング」の重要性が高まってきています。
そこで今回の記事では、マーケティングや販促活動に関わる人なら必ず知っておきたい「リテンションマーケティングの基本と施策の具体例」について紹介します。
この記事をお読みいただければリテンションマーケティングの基礎を理解し、どのような施策へ活用していくべきかといった具体的なアイディアが浮かんでくるはずです。
ぜひ最後までお読みください。
リテンションマーケティングとは「既存顧客の継続的な利用やリピート利用を促進し、顧客ロイヤルティを高めることを目的としたマーケティング戦略・施策の総称」です。
リテンションは「維持や保持」を表す英語で、マーケティング領域では「既存顧客の維持」を意味しています。
リテンションマーケティングが重視される主な理由は、同じ商品を販売するにしても新規顧客を獲得して買ってもらうより、既存顧客に買ってもらう方が必要なコストが低く、継続的な収益につながるためです。
その裏付けとなるのがマーケティング業界で有名な「1:5の法則」と「5:25の法則」です。
新規顧客獲得にかかるコストは既存顧客を維持するために必要なコストの5倍必要であるという法則。
既存顧客の離反を5%改善すれば、利益率が25%改善するという法則。
この2つの法則はアメリカの大手コンサルティングファームであるBain & Company社の名誉ディレクターを務めたフレデリック・F・ライクヘルド氏が提唱したと言われています。
新規顧客を獲得するためには、そのブランドを認知してもらうための広告費や、商品・サービスへの興味関心を高めるための販促費など、さまざまなコストが必要となります。
一方で既存顧客は既にその商品価値を知っていてブランドに対する愛着もあるため、大きなコストをかけずともリピート購入してくれる可能性が高くなります。
つまり既存顧客の離反による売上減少を新規顧客によって補うよりも、既存顧客のロイヤルティを高めて顧客離れを防ぐことのほうが、利益率を下げずに売上規模の拡大する上で重要であるという理論です。
この2つの施策はどちらも重要で、片方だけに注力すればよいというものではありません。
ただ、ビジネスが置かれている状況や、商品・サービスの特性によってその優先度が異なります。
はじめに既存顧客を維持するリテンションマーケティングを優先すべきシーンの例を紹介します。以下のようなケースでは新規顧客獲得よりリテンションマーケティングを優先したほうが売上が伸びやすいと言えるでしょう。
飲食店やサービス業界などは、そのお店を気に入ってもらえればリピート利用してくれる可能性が高いビジネスです。
コストパフォーマンスを強みにしているビジネスであれば、新規顧客も取り込みやすいですが、高単価・高品質のビジネスでは新規獲得の難易度が上がるため、既存顧客を維持するリテンションマーケティングを優先する方が売上を伸ばしやすくなります。
1人の顧客から定期的にサービスを購入してもらうサブスクリプション型のビジネスモデルの場合は、既存顧客に長期的な価値を提供し継続利用を促すことが重要になります。
例えばITクラウドサービスや、動画や音楽のストリーミング配信サービス、商品の定期購入などのビジネスがそれに該当します。
例えば自動車業界であれば、車検や定期点検、オイル交換などの定期的なメンテナンスが発生します。またBtoBの産業機械などを製造販売するビジネスでも修理や定期メンテナンスなどが必要になるため、すでに商品を納入した顧客を離反させない施策が重要になります。
事業を継続していて、ある程度の顧客リストが既に溜まっている場合は、既存顧客リストに対するリテンションマーケティングを優先させましょう。
逆に既存顧客のフォローアップが不十分だと、休眠顧客や離反客を増やしてしまう可能性もあるので注意が必要です。
オンラインショッピングのように成熟した市場は、競合他社との差別化や価格競争が激しいため、会員の囲い込みによるリピート購入を促し、LTVを高めるリテンションマーケティング戦略が重要となります。
それを実現するためには、
などが重要となります。
もちろんリテンションマーケティングよりも新規顧客の獲得を優先すべきシーンもあります。その例をいくつか紹介します。
新しくはじめたばかりの事業ではまだ顧客自体が少ないので、当然ですが顧客リストが蓄積するまでの間は、新規顧客の獲得に注力したほうがよいでしょう。
市場に出たばかりの新しいジャンルのビジネスは、いち早く顧客を囲い込んだ方が先行者利益を得られますし、顧客リストもこれから獲得するフェーズであることがほとんど。ですので、こういったケースにおいても、リテンションマーケティングより新規獲得を優先した方がよいでしょう。
例えば不動産業界(投資物件を除く)や冠婚葬祭業界のようなビジネスにおいては、既存顧客に一生懸命アプローチしても再購入してくれる可能性は高くありません。
ですので、こういったケースにおいても新規顧客の獲得を優先した方がよいでしょう。
ここからはリテンションマーケティングの具体的な施策例を5つ紹介します。
メールマーケティングは、ニュースレターやプロモーション情報を定期的に配信することで、顧客との接触回数を増やしリピート購入を促す手法です。
またメールマーケティングはアライブの得意分野の1つでもあり、例えばクライアントのシナリオメールを構築したり、誕生日メールやイベント開催情報を配信したりすることにより、クライアントが抱える既存顧客の育成に成功した例がいくつもあります。
SNSの活用もリテンションマーケティングとして有効な手法の1つです。
SNSはフォロワーを囲い込むことができ、コメントやDMなどを通じて双方向のコミュニケーションが気軽にできることが大きなメリットです。
メルマガと同様にキャンペーンや最新情報を発信することもできますし、顧客であるフォロワーからのフィードバックを集めることもできるため、商品やサービスの改善に役立てることもできます。
顧客は自分の意見がそれらの改善に寄与できることで、ブランドに対する愛着が高まるというメリットもあります。
ただしSNSの種類によって匿名性が高いこともあり、冷やかしや炎上など注意すべきポイントがあることも覚えておきましょう。
楽天などのネットショッピングや航空会社のマイルなどでお馴染みですが、ポイントサービスは購入金額の数%をポイント還元し、次回のお買い物や他の関連サービスで利用できる制度です。
また購入金額に応じてポイント還元率が増える会員ステージ制度などを設けているサービスも増えてきており、既存顧客のリピート利用促進に大変効果的な手法です。
以下のような理由で顧客が離反してしまうケースは少なくありません。
それらを避けるために有効な手法がカスタマーサクセス。サービス利用時における顧客のお困りごとをサポートすることで十分な利便性を感じてもらえれば、簡単に他のサービスに切り替える可能性が低くなり、継続的に利用してもらえるようになるという手法です。
例えば、サービスを申し込むと専任の担当者がついて運用コンサルティングを行うケースや、会員専用のサポートページにFAQやチャットボットなどを用意して、問い合わせ対応を充実させるなどのケースがあります。
オフラインイベントも有効なリテンションマーケティング手法の1つ。オフラインイベントで顧客同士の交流の場を提供することで、顧客同士の絆を深めることができますし、自社の新製品やサービスについて実際に触れて体験する機会を創出することにより、顧客のロイヤルティをより高めることができるからです。
コロナ禍を経て、今はオフラインでの交流に対するニーズが高まっていて、オフラインイベントを開催する企業もここ最近増えています。
上の章で挙げたリテンションマーケティングを実現するには、MAツールの活用がオススメです。
MAツールとはマーケティングオートメーションツールのことで、「新規顧客獲得やリード顧客の育成フェーズ等におけるマーケティング活動を可視化し自動化するツール」のことを言います。
アライブもSalesforce社の「Maketing Cloud Account Engagement(旧Pardot)」というMAツールの導入支援を行っていますが、このMAツールを使うことで具体的に以下のような施策を実現できます。
MAツールは商品やサービスを利用し始めたばかりの新しい顧客のロイヤルティを向上させることもできますし、すでにロイヤルティの高い優良顧客を維持するためにも活用できる便利なツールです。また、MAツールであればこれらの施策を自動化することができるため、人材不足に悩む企業にとっても比較的導入しやすいメリットもあります。
本格的なリテンションマーケティングを検討されている方は、MAツールの活用を選択肢に入れておくことをオススメします。
MAツールでできることや施策例をより詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事もご参考ください。
>> MAツールでできること。アライブの導入サポート実例を交えてご紹介
今回は「リテンションマーケティングの手法と施策の具体例」について解説しましたが、いかがだったでしょうか?
リテンションマーケティングは利益率を下げずに売上規模の拡大する上で重要な戦略ですので、この記事の内容を改めてまとめました。
「これまで新規顧客の獲得ばかりに注力してきた」とか「ここ数年で売上が伸びづらくなってきた」といった課題を抱えている企業様は、ぜひリテンションマーケティングを検討してみませんか?
アライブは効果的にリテンションマーケティングを実現するMAツール「Maketing Cloud Account Engagement(旧Pardot)」の導入支援も行っていますので、ご検討の際はお気軽にアライブまでご相談いただけると幸いです。
